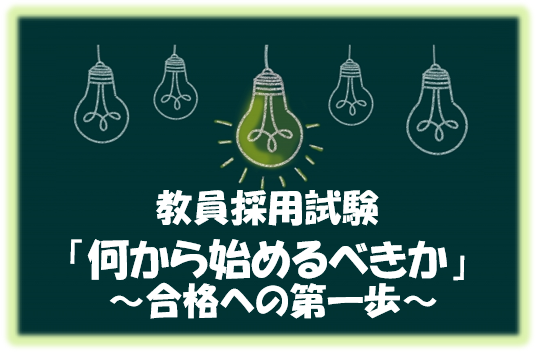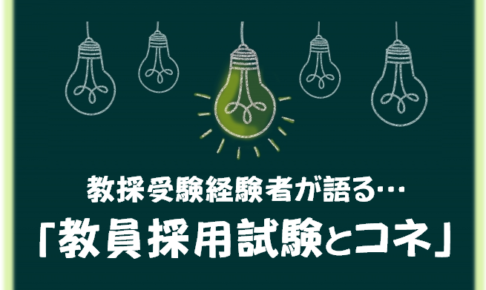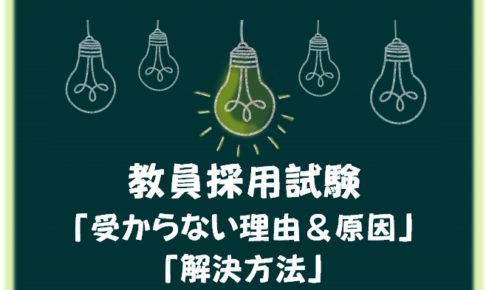教員採用試験は試験科目が多い試験です。
特に小学校の場合は、比較的浅くて広い能力が問われるので

という方が少なくありません。
そこで今回は、教員採用試験対策を始めるのに「何から始めるべきか」を、まとめてみました。
この記事で、効率良く、合格をサクっと手にする第一歩を踏み出してください。
目次
教員採用試験対策では何から始めるべきなのか

教員採用試験対策をスタートする際に、まずこの3点について確認しましょう。
- 受験予定自治体の試験科目
- 試験科目の配点
- 各試験科目に対する自分の力
これらのことを確認せずに
何となくで問題集や参考書を手に取って始めてみたり、「面接があるから」という考えからとりあえず志望動機と自己PRを考え始めたり・・・
という取り組み方は、効率が良くないのでやめましょう。
なぜなら教員採用試験の対策というのは
だからです。
言い換えると「合格のためにどの点を伸ばしていくべきかを明確にする必要があるから」です。
これができれば
「対策を効率良く進める戦略(計画)」
を立てやすくなります。
また、直前期で残された時間が少なくなった時に
「何を優先すべきか」
「何を捨てるべきか」
を適切に判断できるようになります。
例えば、自分の苦手な試験科目の配点が大きければ、その試験科目の対策に時間を掛けなければなりません。
逆に、自信が得意で配点が少ない試験科目があれば「その対策の優先順位は低く設定したほうがいい」という判断ができます。
このように、限られた時間の中で合格を勝ち取る力を効率よく身に着けるためにも、まずは先に挙げた3つのことを確認しましょう。
3つの確認をするためにするべきコト

では次に、3つのことを確認するためにするべきことを具体的に説明します。
するべきことは以下の3つです。
- 受験自治体の試験要項を確認する
- 受験自治体の過去問に取り組む
- 予備校や受験雑誌からの情報で出題傾向を把握する
[1]受験自治体の試験要項を確認

まずひとつめは
です。
みなさんが試験対策をスタートさせる時期には、まだ試験要項が発表されてないことがあります。その場合は昨年のもので良いので、必ず試験要項を確認してください。
もちろん、本年度の試験内容が変更される可能性はあります。しかし、変わったとしても大幅な変更の可能性は極めて低いですし、自治体によっては公表が4月以降になります。
正直なところ、それを待ってもいられません。
試験要項を見ることで
- 試験科目にどのようなものがあるのか
- 配点はどうなっているのか
を確認できます。
例えば、小学校の実技試験で昨年度に「水泳・歌唱・器械体操」の3つが課されていたのであれば、この3つ以外のことが出題される可能性は考えずに実技試験対策を進めましょう。
[2]受験自治体の過去問に取り組む

そして、ふたつめにすべきことは
です。
特に第1希望の自治体の過去問には必ず取り組みましょう。
過去問に取り組むことで
- 自分が受験したい自治体の出題傾向や問題の形式
- 現時点でどれくらいの点数が取れるのか
を確認できます。
面接に関するコトでも
- 面接官の人数
- 面接会場の様子
- どのような質問がされたのか
を確認できることもあります。
ちなみに、過去問を取り組む上で参考にできるオススメ問題集は、協同教育研究会が出版している「教員採用試験の過去問シリーズ」です。
この本は、過去5年分ほどさかのぼって、筆記試験で出題された問題が全てそのまま掲載されています。 面接や論作文でも出題テーマや質問内容などが載っています。
[3]予備校・受験雑誌の情報で出題傾向を把握

そして3つ目は
です。
特に、教職教養や専門試験といった筆記試験では、自治体によって出題分野に偏りがあります。
例えば、教職教養の教育法規に「教育基本法の教育の目標」という出題されやすい分野があるのですが、福島県ではほぼ毎年出題されている一方で、秋田県では過去数年間全く出題されていません。
同じく「教育史」について触れておきますと、長野県・京都府・岡山県・広島県では出題率が低いですが、青森県・秋田県ではほぼ毎年出題されています。
このような 出題傾向を知らず、やみくもに対策を進めることは効率面でかなりのハンデ になります。
この出題傾向を知るために参考になるのは
です。
受験生の間でも有名なこの2誌では、自治体別の出題傾向がひと目でわかるよう、表やグラフなどで整理された特集記事が掲載されます。
教採予備校でも同じような情報が提供されているはずです。
通われている方は積極的に活用し、効率の良い対策をすすめましょう。
[番外編]脳科学から学習法や習慣術を学ぶ
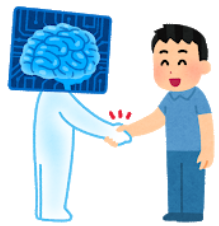
そして最後に番外編。
これは、意外と軽視する人が多いですし、意外と差がつくポイントだと思います。
それは
です。
現代は脳科学が発達して、そこでの研究成果が一般の人の学習成果を変えています。
- 暗記力を高める方法
- 集中力を高める方法
- 勉強を習慣化する方法
といった勉強の効率をアップあせるノウハウが、体のメカニズムを論拠として解明されています。
特にスポーツではその傾向がハッキリしています。
- 筋トレにうさぎ跳び
- 練習中に水を飲んではいけない
- 休養なしで毎日朝から晩まで練習漬け
といった、昔なら当たり前にされていたことが、スポーツ科学によって否定され、効果をあげています。

受験勉強も同じです。
私が受験生だった頃は

- 朝はシッカリ飯食って栄養を取ってから勉強頑張るで!
- 休憩時間はゲームでリラックスや!
- 時間が無いなら寝る間を惜しんででもやる!
といった感じで、論拠の乏しい精神論や迷信で突き進んでいた記憶があります。
でも、今なら

- 朝は軽く外を散歩してから頭を使う対策をし、朝食はひといきついてからバナナとナッツ。
- 休憩時間は5分間アイマスクで目を覆ってリラックス。
- 1日7時間は絶対に寝る。
となっているでしょう。
今なら、本や動画でたくさんの情報があふれています。

みなさんも自分に合った「学習法や習慣術」を見つけて、同じやるなら効率良く対策を進めてください。
目の前にある「多くの課題」に惑わされず、確実な一歩を踏み出そう

教員採用試験は小学校を中心に課される試験科目が多く、個々に抱える課題も多くなりがちです。なので、何から始めるべきなのかを整理しきれず、惑わされる受験生が少なくありません。
惑わされたまま対策を進めたり、何も考えずに無計画に進めると、試験本番に「穴だらけの自分」が出来上がってしまいます。
大切なことは
です。
今回ご紹介した「教員採用試験で何から始めるべきか」について、ポイントを押さえながら、合格への確実な一歩を踏み出してください。
みなさんの合格を願っています。
頑張ってくださいね。
▼教員採用試験にあるウワサ「コネの存在」への向き合い方について考えたい方はコチラ
▼教員採用試験に合格しない人の特徴から学びたい方はコチラ
2025