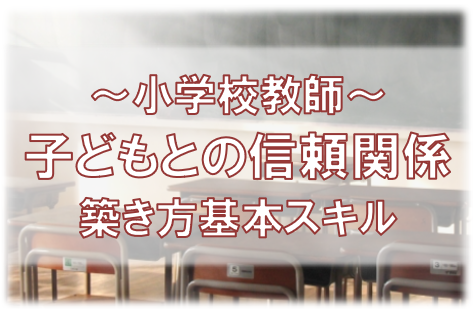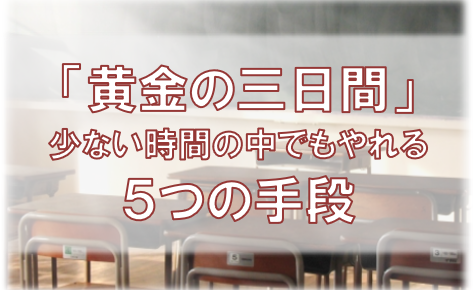教師にとって、子どもたちとの信頼関係を築くことは、安定した学級運営を進めていくうえで欠かすことのできない大切な要素です。
そこで今回は、現役小学校教師の私が
 子どもたちと信頼関係を築くために
子どもたちと信頼関係を築くために
心がけていること
について、まとめてみました。
どれも些細なことですが、日々の教育活動の中で効果を実感していることばかりです。
特に小学校に勤務をする新任教師の方、子どもたちとの関係構築に苦労されている先生方は参考にしてみてください。
目次
日常のコミュニケーションの中で「大切に思われている」と実感させよう

我々教師と子どもたちとの間に信頼関係を構築するためのコツは
です。
経験の浅い先生は
- 手作りプレゼントをする
- 一緒に遊ぶ
- 過度にほめる
- 厳しく叱らない
といったことをやってしまいがちです。
しかし、それは違うと私は考えています。
手作りのプレゼントをしても、一緒に遊んでも、過度にほめてやっても「自分は先生に大切に思われている」という実感が無ければ信頼関係の構築にはつながりません。
そのためには、一緒に遊んだとすれば、遊ぶ中で子どもたちとどのような接点を持ち、どのようなコミュニケーションを取るかが大切です。
一緒に遊んでいるだけでは信頼関係は構築できません。
時間を共有する中で「子どもたちと、どのようなコミュニケーションをするか」が大切なのです。
教師であれば、毅然とした態度で厳しく指導をすることも必要です。
それでも「担任は〇〇先生がいい」と思わせるレベルの信頼関係を築くためには、日常生活でのコミュニケーションを通して「自分は先生に大切に思われている」と実感させることがイチバンの近道です。
では、具体的にどうすれば良いのか。
そのための方法として、現役小学校教師の私が心がけているコトを以下に紹介します。
子どもたちと信頼関係を築くためのコミュニケーション法6つ
子どもたちと信頼関係を築くために、コミュニケーションする上で私が「大切にしていること」は以下の6つです。
- 絶対”微”笑顔
- 視線を合わせる
- 相槌を入れる
- オウム返しをする
- 共感の言葉を入れる
- 話の切り方に気をつける
それぞれについて詳しく説明をします。
ぜひ参考にしてください。
①絶対”微”笑顔

私は、子どもたちとコミュニケーションを取る時だけでなく、基本的に
「笑顔」
で生活することを心がけています。
そして、その安心感の継続は「近づきやすさ」を感じさせることにつながり、子どもたちから精神的にも物理的にも自然と距離を近づけてくるきっかけになります。
そんな中、気を付けているのは「自然な笑顔であること」です。
もちろん、嬉しい時や楽しい時の満面の笑みは必要です。
しかし、普段「愛想よくすること」に慣れていない人は、必要以上に「満面の笑み」を出してしまいがちです。
しかし、それは疲れます、
子どもたちから見ていても無理があります。
私は普段から愛想の良さを継続できるよう「微笑」でいつづけられるようにしています。
具体的には
目元に少し力を入れて
口角を少し上げる
それだけです。
もちろん、子どもたちとの会話の中で「子どもたちにとって楽しいシーン」があれば満面の笑みで対応しています。それ以外に挨拶をしたり、子どもからの話を聞いたりする時などは基本的に「微笑」を心がけています。
②視線を合わせる

子どもとコミュニケーションを取る時に
「視線を合わせること」
も大切です。
どんなに忙しくても、気が向かなくても、子どものとミュニケーションをとる時は視線を合わせましょう。
宿題チェックなど作業をしている時に子どもが何気ない話をしてくることも多々あります。
そんな時、自分がどんなに忙しくても、話の節目に目をあげて数秒だけでも視線を子どもに合わせて話をします。
そうすることで「話を聞いてもらえている」という実感を持つようになり、その実感が子どもたちが教師に感じる「精神的な距離感」を縮めてくれます。
また、相談事などの慎重に対処すべき状況であればあるほど、視線の高さを合わせて話をします。
視線を合わせることは、自然と「自分への思いやりや優しさ」を感じさせる効果があります。
時には膝をついたり、一緒に教壇に座ったり・・・状況に応じて「視線を合わせる工夫」を心がけています。
③相槌を入れる

子どもと会話をしている時、特に長い話を聞いている時には
「相槌を入れる」
ことも大切です。
相槌を入れることは、視線を合わせることと同様に「話を聞いてもらえている」という実感を子どもに持たせることができます。
相槌は
- 首のタテ振りと「うん」など、単純な声の相槌
- 「へー」「なるほど」「ホント?」など、少し感想を入れた相槌
をバランスよく入れることを心がけています。
子どもを相手にしている場合は、首を縦に振るだけの無言の相槌はしません。
声に出して「聞いているよ」という発信を、確実に子どもが受け取れるようにしています。
また、特に2つめの「少し感想を入れた相槌」は、会話の節目に少し入れるだけで「話を聞いている感」を強く発信できるので強く意識しいます。
ぜひ実践してみてください。
④オウム返しをする

「オウム返し」とは、相手の話を繰り返すという「傾聴技術」のことです。
主には
- 話を聞いてもらえている実感を相手に与える
- 共感してもらえている実感を相手に与える
- 聞く側が話を正しく理解できていることの確認
- 話の交通整理
といった効果があります。
例えば


という感じです。
オウム返しは「相手の話の重要なところ」で使います。
単発の話であればその都度使っても違和感がありません。
しかし、長い話の中で使いすぎると、話のやりとりにぎこちなさが出てくるので、使うタイミングや回数には気を付けたいところです。
⑤共感の言葉を入れる

先述した「相槌」や「オウム返し」をする時に発する言葉の中に
「共感の言葉」
を入れることを心がけています。
そうすることで「相槌」や「オウム返し」に深み?を持たせることができます。
例えば


という感じです。
この場合、子どもは今まで勝てなかったA君に勝った「喜び」を伝えたかったと推測して、こちらから発するオウム返しに「うれしい」という共感の言葉を入れます。
トラブルでの相談の場合は


という具合にサラっと相手の気持ちを言葉で言い換えてあげるようなイメージです。
このように「共感の言葉」を入れるだけで、子どもたちの先生への信頼感がググっとアップすること間違いありません。
⑥話の切り方に気をつける

子どもたちとコミュニケーションを取ることは、学級経営を安定させるために欠かせないことです。
しかし、子どもたちとの関係が深まるほど、子どもたちは担任に近づき、イロイロと自分から話をするようになります。
そして、自ら担任教師とコミュニケーションを取りにくる子どももたちで溢れかえります。
時には複数の子どもたちが同時に話しかけてきて、お互い譲らずにずっと話を続けられることも・・・
そんな時には仕事の優先順位を考え、子どもたちの話を途中で切らなければならないこともあります。
そんな時は、できるだけ子どもたちが傷つかないよう
話を断られたことに
納得がいくような切り方
ができるよう気をつけています。
コツとしては「あなたの話を聞きたい」という気持ちの入った一言を入れると良いでしょう。
例えば

といった感じです。
時には、児童に指導をしている時に遠慮なく雑談を入れてくる子どももいます。そういった場合は次のように「優先順位」を伝えることも大切です。

子どもは「先生に聞いてほしい 」「先生と話がしたい」という気持ちで話しかけてきます。
時には、空気の読めない幼い子どもたちに気持ちが揺れることもあります。
しかし、感情的にならずに交通整理をしていくことが大切です。それが子どもたちの気持ちを大切にし、自尊感情をはぐくむことにつながります。
まとめ:上手なコミュニケーションの積み重ねが教師と子どもの信頼関係を築く

教師として学級をまとめるためには、子どもたちひとりひとりとの信頼関係を築くことが大切です。
そして、信頼関係を築くためには「自分が大切にされている」ということを、実感させることが大切であり、そのためには日々のコミュニケーションを上手にこなしていくことが近道です。
今回挙げた6つのポイントは、何れもちょっとした心がけでできることばかりだと思いませんか?
目の前にある雑務をこなしたい気持ちをグッとこらえて、話しかけてきた子どもたちの声に目と耳と体・・・そして心を傾けてあげてください。
その積み重ねがきっと教師と子どもとの信頼関係を土台にした、安定した学級経営の基礎になることでしょう。
🔽「黄金の三日間」で最も優先すべきことについて知りたい方はコチラ