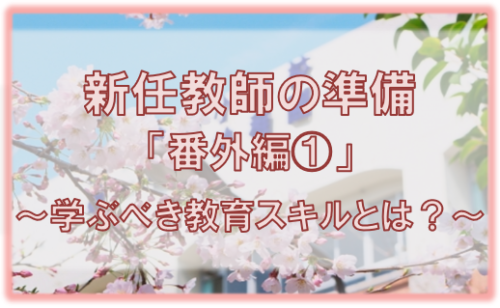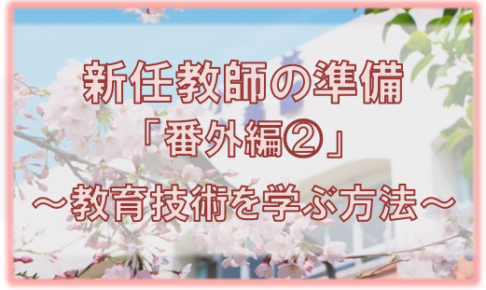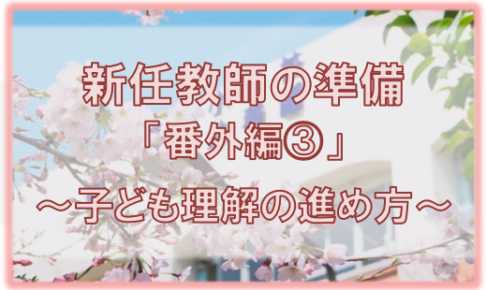教採合格後、着任までの日々を過ごす新任教師のみなさん

と思っている方に向けて、新任教師が着任準備として学んでおくべき教育関係の知識や経験をご紹介します。
教師人生の好スタートを切るために、ご自身に必要なことが何であるかを考えるきっかけになれば幸いです。
目次
新任教師が着任準備として学ぶなら「教育技術」と「子ども理解」

新任教師が着任準備として、教育に関する知識や経験を学ぶのであれば
がオススメです。
新任教師が着任までに学んでおくべき「教育技術」とは?
まず「教育技術」についてお話しましょう。
「教育技術」と「教科知識」の違い

本記事でお伝えしたい「教育技術」と「教科知識」との違いを説明することで、着任までに新任教師が学ぶべき「教育技術」が何であるかをお伝えします。
ここで言う「教育技術」とは、子ども達をコントロールするための方法 のことです。
例えば
- 分かりやすく知識を教えるコツ
- 効果的な叱り方(ほめ方)
- 崩壊しない学級経営のコツ
といったものです。
コントロールというと聞こえが悪いですが、どのような子どもでも前向きに学校生活を送れるようにするための方法と考えてもらえたら良いでしょう。
そして「教科知識」とは、授業を通して子どもたちに教える知識 のことです。
例えば
- 漢字や文章の書き方
- 面積の求め方
- リトマス試験紙の色変化
といったものです。
それぞれの単元での指導内容(面積の公式は結論から教えずに、図形をヒントに子どもたちが自分で考えて公式を導き出せるように授業を進める)も「教科知識」と考えます。
つまり、ここで言う「教科知識」とは教科書の指導書(教師用教科書)に載っている内容と考えてください。
なぜ「教育技術」なのか

新任教師が着任までの準備として学ぶのであれば「教科知識」よりも「教育技術」を優先することをオススメします。
なぜなら
です。
逆に「教科知識」は、身に付けたものによっては着任した年度では使わない可能性が高くなるものあります。
例えば、小学校は6学年あります。
教えるべき知識の範囲を全部押さえても、単純に考えて6分の1の知識しか1年目は使いません。

そして小学校の場合は、知識の深さが浅いです。
なので、既に知っているのものが多く、確認レベルで終わることが多いです。つまり、着任してからのスキマ時間で取り組んでも間に合うことがほとんどなのです。
そう考えると、やみくもに教科知識を頭に入れようとするよりも、遊びたいざかりで、集中力が散漫になりがちな子ども達や、思春期で心が安定しない子どもたちをコントロールする方法…というような「教育技術」を学んでおくほうが、着任後の教師1年目に役立つ可能性が高いということです。

中学校や高校は「教科知識」も必要?

とは言え、中学校や高校の場合、求められる知識レベルは小学校より深くなります。
これは、私の知り合いの高校教師の話ですが
高校では、教科書レベルを超えた知識が無いと、授業で教えるべきコトを伝えるのが難しかったり、生徒の疑問を解消できなかったりする場合があるそうです。
そういう意味では、中学校と高校、特に高校では着任前に教科知識を増強しておく価値はあります。
しかし、小学校と同様に教科知識は受け持つ学年によっては着任した年度で使わない知識があります。そして、学ぶ知識の深さが増すほど、その知識が役に立つ確率は低くなります。

例えば社会科で地理も歴史も政治経済もメッチャ頑張って大学研究レベルまで準備したのに、初年は地理しかやりません・・・となると、コストパフォーマンス悪すぎだと思いませんか?
新任教師に深い知識が不要だと言ってるのではありません。
そもそも、私たちは教採の専門試験対策で、必要な知識はある程度学んでいるはずで、それ以上の知識を「着任準備」として学ぶ価値がどれだけあるのか・・・という話です。
正直、そこまでしなくてもいいだろうし、もっと学ぶべきこと(役立つ可能性の高い知識)があるのではないか・・・と思います。
どうしても教科知識を増やすなら・・・

それでも

という中学や高校に着任予定の方はいるでしょう。
特に高校で進学校に配属された場合のことを考えると不安で珠ないと思います。
そんな方は、範囲を絞って教科知識を増やすことで着任準備をススメルと良いでしょう。
具体的には
ということです。
人に教える立場に立つ以上は、自分の担当教科については苦手がないようにしておきたいものです。
教師になって、生徒から教科書範囲の質問をされたにも関わらずシドロモドロになってしまい

と思われたくないですよね。
例えば、高校数学で合格された方でも

というような苦手は誰でもあるはずです。
そういう苦手分野を補強して、自分の担当教科内の苦手を無くしておくことをオススメします。
新任教師が着任までに学んでおくべき「子ども理解」とは?

次に、着任までに進めておくべき「子ども理解」についてお話しましょう。
ザックリと「子ども理解」と言っても、子どもを理解する切り口はたくさんあります。
以下に、教師として進めるべき「子ども理解」の代表的な切り口には以下のものが挙げられます。
- 「年齢・発達段階」に応じた子ども理解
- 「先天的・後天的な障害」に応じた子ども理解
「年齢・発達段階」に応じた子ども理解

まずは
を理解するようにしましょう。
幼稚園を含む就学前に始まり、小学校、中学校、高等学校と、成長していく子ども達には、最大公約数的な特徴があります。
教育心理学で言う
- ピアジェの認知的発達段階説
- フロイトの性的発達段階説
- エリクソンの発達課題説
のようなものです。
今は、これら昔からある理論と現代の研究成果をまとめた発達段階の傾向があるので、それを理解しましょう。

このような年齢・発達段階に応じた子どもの傾向を理解すれば、様々な場面で見せる子どもたち態度のウラにある心の中を想像できるようになり、子どもの実態に応じた対応ができるようになります。
先天的・後天的な障害への理解

次に
を押さえましょう。
着任までに学んでおくべき先天的な発達障害の具体例としては
- ADHD
- アスペルガー症候群
- 自閉症スペクトラム
- 学習障害
といったところが挙げられます。
また、後天的な障害の具体例としては
- 愛着障害
- 摂食障害
などが挙げられます。
障害という括りではないですが、不登校・自傷行為・うつ、自尊感情の低い子どもなどについても着任までに学んでおくべきことに含まれます。
着任までに「子ども理解」を進めておくべき理由

着任までに「子ども理解」を進めておくべき理由は主に以下を挙げることができます。
- 子どもとの間の対応ミスを予防できる
- 着任後のカルチャーショックを和らげることができる
着任後の「子どもとの間の対応ミス」を予防できる

着任後に子どもたちとのかかわりの中で、新任教師にあることに「対応ミス」があります。
例えば、小学校1年生の児童に普段自分が話をする時のスピードと語彙量で話をしても通じません。
また、思春期の生徒児童に時と場合を考えずに正論をぶつけると、心が離れてしまい、本音を教師に言わなくなったり、反抗的になったり、学校に来なくなったりする場合があります。
こういった、教師と子どもとの間の対応ミスを防ぐためにも「子ども理解」が大切です。
特に、初めて教壇に立つ新任教師の方々は、着任までに、相手をするであろう年齢層の子ども理解を進めておくことは、着任後の子どもたちとの関わりで「限りなく正解に近い対応ができる確率」をアップさせることに繋がります。
着任後の「カルチャーショック」を和らげる

新任教師のみなさんは、着任するまでの間は基本的に大人と交流することが中心の生活を送ります。なので、言葉の受け答えなどのコミュニケーションをする時の思考回路が完全に大人脳になっています。
その状態で、着任して学校が始まると、コミュニケーション量の半分以上が子ども相手にガラっと変わってしまいます。
冷静に考えるとアタリマエのことですが
- 理解力
- 運動能力
- 反応
- 心の強さ
- 雰囲気
といった全てのことが大人とは違います。
そのギャップが、カルチャーショックとして心因教師にとって大きな負担になることがあります。
子ども理解を進めておけば

というような感じで受け入れることができ、着任後のカルチャーショックを和らげることもできるのです。
自分に必要だと思ったコトを積極的に学んでいこう

今回は、これから教師として教壇に立たれる方、特に教採に合格した後の着任までの時間の過ごし方として
だということをお伝えしました。
とは言え、教員採用試験と同じで、準備や対策というのは「求められる基準と現状との差分を埋めていく作業」になります。
本記事では、できるだけ多くの人あてはまるよう「最大公約数」的なお話を書いていますので、必ずしもみなさん自身にピッタリ当てはまるとは限りません。
大切なことは、皆さんが着任し、教師として子どもの前に立った時に「子どもにとってプラスの存在」になるための準備をすることです。
そのために、現状の自分を客観視して

と感じたことを積極的に学んでいけば良いのではないかと思います。
本記事が、これから教壇に立つみなさんが準備を進めるにあたって「自分は何を準備すべきか」を考えることに役立ったのであれば幸いです。
新しい教師生活が、みなさんにとって充実したものになるよう願っております。
🔽新任教師が着任前に「教育技術」について学ぶ方法を知りたい方はこちら
🔽新任教師が着任前に「子ども理解」を進める方法を知りたい方はこちら