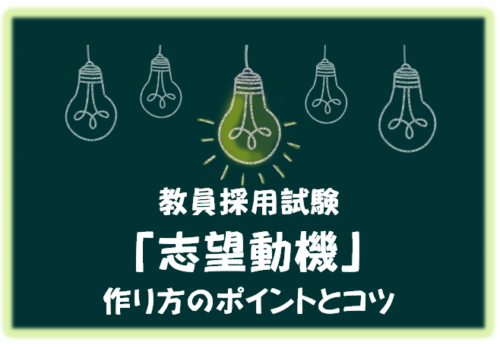教員採用試験の面接対策で「志望動機」を準備することはとても重要ですが、簡単にできることではありませんね・・・
この記事では、教員採用試験を受験予定の方を対象に

合格ラインを越えられる
志望動機の書き方
(作り方)
について、例文を交えてお伝えします。
面接官が納得する志望動機を準備するためのヒントにしてください。
目次
【STEP1】 志望動機を書く前に「先入観」を打ち破ろう

教採に限らず、採用試験に関する先入観はイロイロあります。
その中でも「〇〇すると落ちる・・・」「〇〇にすると合格しやすい・・・」といった先入観は、受験対策の方向性を左右しがちです。
そこで今回は、教採の志望動機を作る上でジャマになる「先入観」を2つ紹介しておきます。
①教採の志望動機は
「立派でなくても合格できる」

志望動機は
立派でないといけない
という先入観を持っていませんか?
多くの教採受験生が、立派な志望動機を作るためのネタがないことに悩んでいます。
なぜなら、ほとんどの受験生には

教師を志望する
立派な動機がない・・・
からです。
殆どの受験生が「仕事に就くとしたら何がいいかな・・・」と考えた時に、他の仕事と比べてみて

と思いついた程度なのです。


という受験生は少数派です。
なので逆に考えてください。
ほとんどの教採受験生に明確で立派な志望動機が無いということは、あなた自身、そのコトに負い目を感じる必要は無いということになります。
そうなんです

志望動機は
立派でなくても
合格できる!
のです。
なので、”今から”一生懸命に考えて、合格ラインを越えることのできる
ありきたりだけど
教師になりたい意思が伝わる
志望動機
を作っていきましょう。
②教採の志望動機に
「タブーはない」

世に出ている志望動機のつくり方に関する意見の中に、「志望動機に〇〇ネタはアウト」という考えがあります。
しかし私は
基本的に
志望動機にタブーは
ない
と思っています。
なぜなら、一般的に「〇〇ネタはアウト」と言われる志望動機を使って合格している人が普通にいるからです。
特によく「アウト」と言われるのは
「尊敬する教師との出会い」
を志望動機に挙げるパターンです。
でも「尊敬する教師との出会い」が本当に教師を目指すきっかけになったのであれば、それは仕方のない話です。
本当にそうなのであれば自信を持って正直に話すべきでしょう。

そもそも「尊敬する教師との出会い」が「志望動機としてアウト」と言われるのには理由があります。
それは「尊敬する教師との出会い」を志望動機とする受験生の多くが、その志望動機について深く聞くと説得力に欠けるケースが多い からです。
志望動機への考えが浅く、小手先で済ませようとする受験生がよく選ぶ志望動機が「尊敬する教師との出会い」なのです。その場合、本当に尊敬するレベルではなく「マシだったという程度の教師」を志望動機に挙げることになるので、面接官によるツッコミの質問を重ねるほど説得力に欠けてくることが多くなります。
なので、結果として試験官や面接指導の経験のある方からすると「アウトなケース」と認識されてしまっているのです。
それでも
基本的に
志望動機にタブーは
ありません
みなさんが本当に教師を志望する理由、きっかけになったコトであり、そこから得たことを将来の教師生活に活かしていきたいのであれば、それが何であっても志望動機として自信を持って発信しましょう。
【STEP2】 志望動機のネタづくりのコツ

それでも教員採用試験に合格するためには「教師になりたい意思が明確に伝わる志望動機」が必要です。
そのような志望動機をどのように書く(作る)べきか、ココから具体的にご説明しましょう。
①「未来」と「過去」
を結び付けるイメージで書こう
まず、志望動機の全体的なイメージですが

「未来」と「過去」を
結びつける
ことを意識して書いてください。
まずは、例文を示します。
<未来>
これまでの経験から、子どもたちが自己肯定感を持って学校生活を送れる手助けをしていきたいと考えたからです。
<過去>
小学生の頃、勉強も運動も苦手で何をするにも後ろ向きな子でした。
しかし、6年生の時に担任だった先生が、普段から頻繁に私に声をかけてくれたり褒めてくれたりしたので、少しずつ気持ちが前向きになり、自分にもやれそうな気がしてきて、学習活動にに前向きに取り組むめるようになりました。そのおかげで今の自分があると思っています。
<未来>
ですので、これからは私が教師として子どもたちに声かけをしたり褒めたりして、子どもたちの自己肯定感を育んでいきたいと考えています。
次に、ココで言う「未来」と「過去」とは何かを具体的に説明をします。
①「未来」とは
「教師観や指導観」

志望動機の「未来」とは「教師観や指導観」のことです。
つまり、志望動機の「未来」とは
自分が教師になったら
「何を大切にして」
指導をしていきたいか
です。
先に示した例文で言うと、青色の部分のことです。
<未来>
これまでの経験から、子どもたちが自己肯定感を持って学校生活を送れる手助けをしていきたいと考えたからです。
<過去>
小学生の頃、勉強も運動も苦手で何をするにも後ろ向きな子でした。
しかし、6年生の時に担任だった先生が、普段から頻繁に私に声をかけてくれたり褒めてくれたりしたので、少しずつ気持ちが前向きになり、自分にもやれそうな気がしてきて、学習活動にに前向きに取り組むめるようになりました。そのおかげで今の自分があると思っています。
<未来>
ですので、これからは私が教師として子どもたちに声かけをしたり褒めたりして、子どもたちの自己肯定感を育んでいきたいと考えています。
他に例を挙げてみると
- 日々のコミュニケーションを通して子どもたちとの信頼関係を築く
- 子どもたちを褒めて自尊感情を育てることを最優先に考える
- 体を動かしたり声を出したりすることを通して子たちに元気と活力をもたらす
などがありますね。
みなさんが教師になったらやってみたいこと・・・それが志望動機の中の「未来」です。
②「過去」とは
教師観・指導観を抱いた
「キッカケ」

志望動機の「過去」は自分が描く「未来」の理由のことです。
つまり、志望動機の「過去」とは
「教師観や指導観」
を抱いたキッカケ
のことです。
先に示した例文で言うと、青色の部分のことです。
<未来>
これまでの経験から、子どもたちが自己肯定感を持って学校生活を送れる手助けをしていきたいと考えたからです。
<過去>
小学生の頃、勉強も運動も苦手で何をするにも後ろ向きな子でした。
しかし、6年生の時に担任だった先生が、普段から頻繁に私に声をかけてくれたり褒めてくれたりしたので、少しずつ気持ちが前向きになり、自分にもやれそうな気がしてきて、学習活動にに前向きに取り組むめるようになりました。そのおかげで今の自分があると思っています。
<未来>
ですので、これからは私が教師として子どもたちに声かけをしたり褒めたりして、子どもたちの自己肯定感を育んでいきたいと考えています。
人の「価値観」はその人の経験によって培われます。
したがって、自分で考えた「教師観や指導観 = 教師になったら何を大切にして指導したいか」が、過去の自分のどの部分(経験)から培われてたのか を考えましょう。
それは何であっても構いません。
ありきたりで、インパクトに欠けることであっても構いません。
- 打ち込んできたクラブ活動での経験
- 今も尊敬する教師との出会い
- 仕事やアルバイトでの経験
- ボランティア活動での経験
- 過去の学校生活での経験
- 熱中してきた趣味を通しての経験
など、誰にでもあるのではないでしょうか。
決して「輝かしい思い出」でなくても大丈夫です。
大切なことは「インパクト」ではありません。地味であっても「説得力」があるコトが大切です。
③考えるのは
「過去」or「未来」
どちらからでもOK!

先ほど、志望動機は「未来」と「過去」結びつけて作る・・・とお伝えしました。
「未来」からつくると結びつく「過去」が見つからないことがあります。なので「過去」を振り返ってから「未来」を作っても構いません。
大切なことは
志望動機の内容で「教師になったら叶えたい自分の未来像」と「教師を志望する動機になった過去の経験」が結びついていること
です。
そこが結びつかなければ、試験官に「ウソの志望動機」と判断されることでしょう。
何となく教師を志望した方は「過去」から考えて「未来」を作るほうがやり易い かもしれませんね。
すでに明確な「未来=教師観や指導観」を持てている人は、その「教師観・指導観」を持つようになった理由について、過去の自分を振り返って考えてみましょう。
それが「きっかけ=動機」です。
志望動機は
「未来と過去を結びつけて」
つくる
コトが大切なのです。
④「過去」は「近い過去」でも良い

「過去」というと、自分が小学校から高学時代などの「遠い過去」を想像しがちですが
志望動機で使う「過去」は
遠い過去でなくてもOK
です。
極端に言えば、昨日のことでもOK です。
例えば、講師経験をしている方は日々の講師経験から「教育観が変化する」ことはあり得る話です。
教師を志望するきっかけになったのが過去のクラブ活動を通して…であっても、過去のクラブ活動での経験と、今自分が思っている教育観とがつながらないのであれば、そのきっかけになった講師経験をあわせて正直に話すと良いでしょう。
例えば
<未来>
志望動機は〇〇なことを子どもたちに伝えていきたいからです。
<過去>
もともとは高校時代のクラブ活動の経験から△△を大切にする教師になりたいと考えていましたが、講師の経験を通して〇〇の大切さを感じ、それを今も実践しています。
<未来>
教師になってからも〇〇を大切にして、子どもたちに接していきたいです。
というような具合で語れば伝わるはずです。
志望動機のキッカケになる過去は遠い過去でなくても良いです。
むしろ近い過去であるほうが、現実的で説得力があるんじゅないかと思うのですが、みなさんはどう思われますか?
【STEP3】簡潔で分かりやすい志望動機に編集するコツ

「未来」と「過去」を結び付けて志望動機がある程度固まったら、文章で簡潔かつ分かりやすく伝えられるように編集しましょう。
①順序は「未来 ⇒ 過去」で

志望動機を書く(つくる)上で大切なコト
それは
志望動機を
「未来 ⇒ 過去」
で展開させる
ということです。
質問内容は「志望動機」ですが、試験官が知りたいのは「受験者の教育観」です。
「受験者の教育観」を知るために「志望動機」を聞いている、ということを意識しましょう。
先ほどから示している例文も、未来から語り始め、過去につなげています。
<未来>
これまでの経験から、子どもたちが自己肯定感を持って学校生活を送れる手助けをしていきたいと考えたからです。
<過去>
小学生の頃、勉強も運動も苦手で何をするにも後ろ向きな子でした。
しかし、6年生の時に担任だった先生が、普段から頻繁に私に声をかけてくれたり褒めてくれたりしたので、少しずつ気持ちが前向きになり、自分にもやれそうな気がしてきて、学習活動にに前向きに取り組むめるようになりました。そのおかげで今の自分があると思っています。
<未来>
ですので、これからは私が教師として子どもたちに声かけをしたり褒めたりして、子どもたちの自己肯定感を育んでいきたいと考えています。
※上記は、小学校教師になりたい理由(志望動機)の例文になっています。
こんな要領で作れば、スッキリと「あなたが教師になったら何をしたいのか=教師になりたい理由」が伝わる志望動機にりますね。
②長さに応じて複数パターンを準備する

志望動機だけではありませんが、面接で言うことが決まっている事柄については、求められる長さに応じてパターンを作っておくと良いでしょう。
特に「志望動機」と「自己PR」は最低でも以下のパターンを想定して作っておくべきでしょう。
- 15秒
- 30秒
- 60秒
基本的には「15秒、30秒、60秒」の3パターンで十分です。
しかし、よくある志望動機ほど個性が問われます。
特に1分程度の志望動機を語るパターンを作る場合には

具体的なエピソードを入れる
と個性が出て良いでしょう。
また、深く突っ込まれた時に、様々な観点から具体的に語れるよう、志望動機に関わるエピソードについてはシッカリと振り返り、その経験や経験から得た価値観を教育現場のどのような場面で活かしていけるか を整理しておくことが大切です。
例えばこんな質問にサラっと応えられるよう準備しておくと良いでしょう。
そのあなたの考えを、学校の教育現場のどの場面で活かしていけると考えていますか?具体的にひとつ教えてください。
【CHECK!】理想は「志望動機」で語る教師観・指導観が他質問への返答と結びつくコト

最後に、志望動機が合格できるモノになっているかどうかをチェックする基準をお伝えしておきます。
というのも「志望動機」は志望動機を聞かれた時だけ答えているようでは「志望動機として弱い」です。
志望動機を基にした「教師になったらやりたいコト=教育観や指導観」が他の質問への返答でもにじみ出るようにする
のが理想です。
例えば、志望動機で

子どもたちのとのコミュニケーションを大切にし、自尊感情を育む教育をしていきたい
と答えた以上、他の質問に対する答えも「子どもたちとのコミュニケーションを大切にして自尊感情を育む教育」を基にした返答ができると理想的です。
そうすることで 志望動機に説得力 が生まれ、試験官に自分のことを理解してもらいやすくなります。
分かりやすさは大切です。
みなさんが面接会場を出られた後、試験官が

というイメージを持ってもらえたら最高ですね。
【LAST】立派でなくても「明確な志望動機」は教採攻略の大きな戦力

いかがでしたか。
今回は教員採用試験を攻略するために必要不可欠な「志望動機」の作り方(書き方)について説明しました。
立派でなくても
「明確で説得力のある志望動機」
は、特に教員採用試験の面接試験では大きな戦力になります。
片手間でパパッと作ってしまうのではなく、過去の自分を振り返りながら・・・そして、自分の理想の教師像を描きながら時間をかけて作ってみてください。
もちろん、試行錯誤しながら「途中変更」するコトもありです。大アリです。

教員採用試験の面接官にみなさんの魅力が伝わる「志望動機」がつくれること、そしてみなさんが教員採用試験に合格されることを願います。
がんばってくださいね。
▼教員採用試験で勝てる「志望動機」の作り方について、Youtube動画で学びたい方はこちら。
※三自治体を三連勝一発合格した本サイト管理人が使用した志望動機を公開しています。
▼華やかな実績が無くても勝てる自己PRの書き方について知りたい方はこちら