教員採用試験で出題される教職教養に関する資料を穴埋め形式で学習できるよう、まとめました。

ここでは

児童の保護・育成
に関する問題を掲載しており、具体的には以下の内容を問題にしています。
- 児童虐待の防止等に関する法律(虐待の定義・発見・通告など)
- 児童福祉法(児童の保護・育成と責任)
- 教育基本法・学校教育法(地方公共団体による援助)
重要なポイントは赤字にしているので、赤シートをスマホやタブレットの上にかぶせると消えます。
チェック教材の代わりにしてください。
同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。
目次
「児童虐待の防止等に関する法律」より
「児童虐待の防止等に関する法律」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条
~法律の目的~
この法律は、児童虐待が児童の( 人権 )を著しく侵害し、その( 心身の成長 )及び( 人格の形成 )に重大な影響を与えるとともに、我が国における( 将来の世代 )の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の( 禁止 )、児童虐待の( 予防 )及び( 早期発見 )その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の( 保護 )及び( 自立 )の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって( 児童の権利利益 )の擁護に資することを目的とする。
第2条
~児童虐待の定義~
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(( 18 )歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条
~早期発見~
第1項
学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び( 学校 )の( 教職員 )、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を( 発見 )しやすい( 立場 )にあることを自覚し、児童虐待の( 早期発見 )に努めなければならない。
第2項
前項に規定する者は、児童虐待の( 予防 )その他の児童虐待の( 防止 )並びに児童虐待を受けた児童の( 保護 )及び( 自立 )の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
第3項
第1項に規定する者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する( 秘密 )を漏らしてはならない。
第4項
前項の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第2項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力するように努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
第5項
学校及び児童福祉施設は、( 児童 )及び( 保護者 )に対して、児童虐待の防止のための( 教育 )又は( 啓発 )に努めなければならない。
第6条
~通告~
第1項
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する( 福祉事務所 )若しくは( 児童相談所 )又は( 児童委員 )を介して市町村、都道府県の設置する( 福祉事務所 )若しくは( 児童相談所 )に通告しなければならない。
「児童福祉法」より
「児童福祉法」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第1条
全て児童は、( 児童の権利に関する条約 )の精神にのつとり、適切に( 養育 )されること、その( 生活 )を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその( 自立 )が図られることその他の( 福祉 )を等しく保障される権利を有する。
第2条
全て( 国民 )は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の( 年齢 )及び( 発達 )の程度に応じて、その( 意見 )が尊重され、その( 最善の利益 )が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の( 保護者 )は、児童を心身ともに健やかに( 育成 )することについて( 第一義的責任 )を負う。
③ 国及び( 地方公共団体 )は、児童の( 保護者 )とともに、児童を心身ともに健やかに育成する( 責任 )を負う。
「教育基本法」より
「教育基本法」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第4条
第3項
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( 経済的理由 )によって( 修学 )が困難な者に対して、( 奨学 )の措置を講じなければならない。
「学校教育法」より
「学校教育法」の原文を確認されたい方はコチラ。
以下、出題される可能性の高い部分の穴埋め問題です。
第19条
( 経済的理由 )によつて、( 就学困難 )と認められる学齢児童又は学齢生徒の( 保護者 )に対しては、( 市町村 )は、必要な( 援助 )を与えなければならない。
🔽同じタイプの「時事問題編」をご利用になりたい方はコチラの記事をご覧ください。

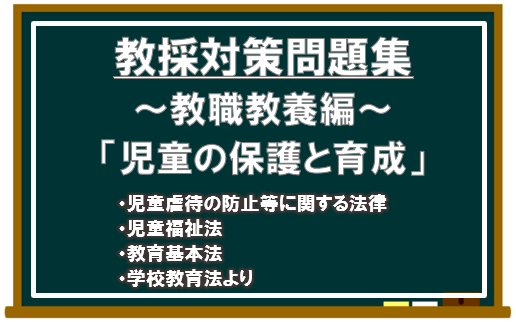
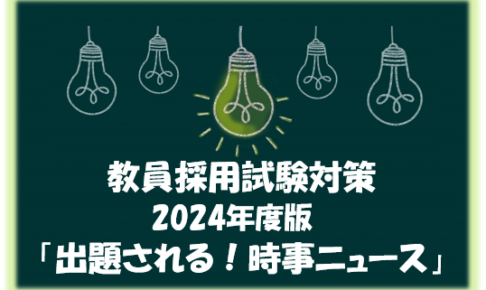
はぜひご利用ください。